 平成16年度藤本倫子環境保全活動助成基金報告集一覧
平成16年度藤本倫子環境保全活動助成基金報告集一覧
|
エコクッキング教室の様子 おもちや、おせちでおやつを作る  土のう袋堆肥づくり講座  |
||||||||||||||||
|
環境保全型水田づくり 里山保全活動  2月のシンポジウムの様子  |
||||||||||||||||||||
|
200号記念誌 「なかうみ」  本庄川での水生生物調査  韓国の子ども達と「中海」の水質調査  |
||||||||||||||||
|
思い思いに生き物と触れ合う子供たち  ヒトデの口を探す園児たち  |
||||||||||||||||||
|
生産地を訪ねる スウェーデンからのエコメッセージ  日本の朝ごはんを作ろう  |
||||||||||||||||
|
風力発電の先進地を訪ねて 講座でのディスカッション  市民共同発電所の前で  |
||||||||||||||||||
|
燃料電池模型の展示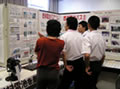 地産地消についての展示  ソーラークッキング  |
||||||||||||||||
|
親竹として残す杭の製作 竹林教室メンバー集合  小学3年生が、ノコギリで竹の間伐  |
||||||||||||||||||
|
「エコフレンドリークッキング」食べたあとのゴミの重さを量る 「いのちのつながり ~鰯の手開き~」 鰯を自分達で開く。  大学生達と、エコフレンドリーな遊び場を企画・運営  |
||||||||||||||||||
|
冊子「家庭からでるやっかいなごみ」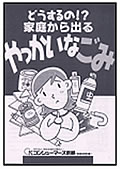 蛍光管・乾電池の処理工場の見学会   |
||||||||||||||||||
|
eファイル 研修会の様子   |
||||||||||||||||||
|
「手のひらから生まれる みどり妖怪シードロ」 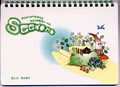  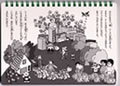 |
||||||||||||||||||
|
五右衛門風呂の風呂焚き カマドでご飯焚き  萩岳頂上で長崎原爆の話を聞く  |
||||||||||||||||
|
リセットクリーンアップの風景 パネルディスカッションの様子  会場からの熱心な質問  |
||||||||||||||||
|
植樹の様子 防護ネットの設置  防護ネットの準備  |
||||||||||||||||
|
アクティビティ 「ハンプティダンプティ」  アクティビティ 「驚異の旅」  アクティビティ 「水のオリンピック」  |
||||||||||||||||
|
聞き取り調査の様子 冊子の内容 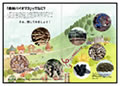 作成した白書と冊子 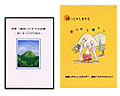 |
||||||||||||||||||
